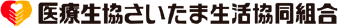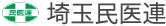患者の権利
医療は、患者と医療従事者が互いに人間としての尊厳を尊重しあい、信頼に基づく協同関係によって成りたつものです。患者には、療養の主体者としてここに掲げる権利があります。当院では、これらの権利を患者が適切に行使できるよう、患者と医療従事者が協力してその実現に努力します。
- 良質な医療を受ける権利
患者には、あらゆる差別を受けることなく、安全で適切な医療を受ける権利があります。これらの権利の保障は、日本国憲法に基づき、国及び自治体が義務を負うものであり、患者には、医療福祉制度の改善や充実を要求する権利があります。 - 知る権利
患者には、病名、病状(検査の結果を含む)、予後(病気の見込み)、診療計画、処置や治療方法(選択の理由、その内容、危険性、他の選択肢)、 薬の名前や作用・副作用、必要な費用などについて、十分に説明を受ける権利があります。
また、自己に関する、診療録・検査結果・画像資料等を含む全ての医療記録の開示を求める権利があります(カルテ開示)。 - 学習する権利
患者には、健康や疾病、療養方法や予防方法、医学的知識や医療制度、社会保障制度などを学ぶ権利があります。 - 自己決定権
患者には、十分な説明を受けた上で、医療従事者の提案する治療方法等に同意あるいは選択、拒否する権利があります。 患者には、自己決定にあたり、いつでも主治医以外の医師の意見(セカンドオピニオン)を聞く権利があります。また、自己決定した後も医療従事者の支援を受けることができます。 - 自己情報コントロール権
患者には、医療従事者が医療の提供過程において取得した自己の個人情報を保護され、その取り扱いについて自ら決定あるいは配慮を求める権利、および私的なことに干渉されない権利があります。
2012年10月29日 埼玉協同病院
医療福祉生協の「いのちの章典」
はじめに
日本生活協同組合連合会医療部会は「医療生協の患者の権利章典」「医療生協の介護」を策定し、事業と運動の質を高めてきました。これらの活動を引きつぎ、2010年日本医療福祉生活協同組合連合会(医療福祉生協連)が発足しました。
医療福祉生協は、いのちとくらしを守り健康をはぐくむ事業と運動を大きく広げるため、これらの成果を踏まえ、医療福祉生協連の設立趣意書の内容を基本にして 「医療福祉生協のいのちの章典」(いのちの章典)を策定します。
「いのちの章典」は、憲法をもとに人権が尊重される社会と社会保障の充実をめざす、私たちの権利と責任を明らかにしたものです。
医療福祉生協とは
医療福祉生協は、地域のひとびとが、それぞれの健康と生活にかかわる問題を持ちよる消費生活協同組合法にもとづく自治的組織です。医療機関・介護事業所などを所有・運営し、ともに組合員として生協を担う住民と職員の協同によって、問題を解決するための事業と運動を行います。
医療福祉生協が大切にする価値と健康観
私たちは、近代市民社会の大原則であり、日本国憲法の基本理念である主権在民の立場にたちます。私たちは、憲法13条の幸福追求権や9条の平和主義、25条の生存権を実現するため、主権在民の健康分野の具体化である健康の自己主権を確立します。
私たちが大切にする健康観は「昨日よりも今日が、さらに明日がより一層意欲的に生きられる。そうしたことを可能にするため、自分を変え、社会に働きかける。みんなが協力しあって楽しく明るく積極的に生きる」というものです。
私たちは、この価値と健康観にもとづき、医療・介護・健康づくりの事業と運動をすすめ、地域まるごと健康づくりをめざします。
いのちとくらしを守り健康をはぐくむための権利と責任
ともに組合員として生協を担う私たち地域住民と職員には、いのちとくらしを守り健康をはぐくむために、以下の権利と責任があります。
自己決定に関する権利
私たちは、知る権利、学習権をもとに自己決定を行います。
自己情報コントロールに関する権利
私たちは、個人情報が保護されると同時に、本人の同意のもとに適切に利用することができるようにします。
安全・安心な医療・介護に関する権利
私たちは、安全・安心を最優先にし、そのための配慮やしくみづくりを行います。
アクセスに関する権利
私たちは、必要な時に十分な医療・介護のサービスを受けられるように社会保障制度を改善し、健康にくらすことのできるまちづくりを行います。
参加と協同
私たちは、主体的にいのちとくらしを守り健康をはぐくむ活動に参加し、協同を強めてこれらの権利を発展させます。
2013年6月7日
日本医療福祉生活協同組合連合会 第3回通常総会にて確定
- ホーム
- 患者の権利・いのちの章典