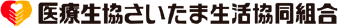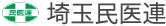用語の注解
用語の注解およびこれまでの倫理委員会における考え方の整理
ここに挙げた用語は、必ずしも広く認められた、定義の確立したものとは限りません。01年度に倫理委員会が発足して以降、公開倫理委員会や学習会も含め、さまざまなテーマで論議し考え方をまとめてきました。臨床倫理的な問題を討議する際に、一つの語を各自が異なった意味で理解し用いると混乱を生じます。このような混乱を避け、倫理的な問題を適切に検討する助けとするため、倫理委員会におけるこれまでの討議の到達を踏まえて、日常使用される用語を以下にまとめました。さらに、倫理委員会の討議の中で考え方を整理してきた事項(テーマ)についてまとめました。
基本的な用語の注解
1.
-
自律
〔高石.患者の自己決定権についての考察.民医連医療No.351〕
自分で自分の行為を規制することであり、外部からの規制などによらず、自身の立てた規範に従って行動すること、自ら普遍的道徳法を立ててこれに従うこと。
2.
-
道徳
〔高石.患者の自己決定権についての考察.民医連医療No.351〕
法律のような外面的強制力を伴うものではなく、社会に対する、あるいは成員相互間の行為の善悪を判断する基準として、一般的に承認されている規範の総体のこと。
3.
-
医師に課せられている注意義務
〔高石.患者の自己決定権についての考察.民医連医療No.351(改)〕
予見的義務:ある患者の病状のその後を予測すること
危険回避義務:予測される事態に対して、患者の不利益になるような結果を回避すること
上記二種類の他に説明義務も含まるというのが一般的である。
4.
-
意思と意志
〔高石.患者の自己決定権についての考察.民医連医療No.351〕
意思:法律で」そうしたい(したくない)という本人の気持ち。「意思表示」とは、契約の申し込み・解除や遺産相続など、権利、義務についての法的効果を生じさせるために、何らかの方法で外部に本人の意思を表明すること。
意志:困難や反対があっても、最後までやり抜こう(絶対にすまい)という、積極的な意向のこと。
5.
-
患者の推定的意思
※参考.東海大学安楽死事件判決.横浜地裁
〔高石.患者の自己決定権についての考察.民医連医療№351,01第5回高齢者の終末期医療 P14〕患者自身の明確な意思表示が存在しないときに、患者の推定的意思によることを認めるとするもの。推定的意思の認定は、「患者の性格、価値観、人生観などについて十分に知り、その意思を適確に推定しうる立場」にあり「患者の病状、治療内容、予後等について、十分な情報と正確な認識を持って」いて、「患者の立場に立った上での真摯な考慮に基づいた意思表示」ができる者により補って行なう必要があり、患者および家族に関する情報を収集し蓄積した上で、複数の医師および看護師等による集団的な検討をもって適確な認定が行なわなければならない。疑わしい場合は、生命の維持を優先させ、意思の推定に慎重さを欠くことがあってはならない。
6.
-
リビングウィル
〔高石.患者の自己決定権についての考察.民医連医療№351,02第5回患者の意思を尊重するとは P17〕
患者が無能力となった場合に、患者がいかにして特定の決定をしてもらいたいと望んでいるかを記した指示書(終末期要望書と同一ではない)。日本では「リビングウィル」を終末期要望書の意で使われることが多い(02年度P17「リビングウィル」は終末期要望書とほぼ同義)
※アメリカでは、州法によって拘束力に差がある。
7.
-
自己情報コントロール権
〔高石.患者の自己決定権についての考察.民医連医療№351〕
自己に関する情報を「いつ、どのように、どの程度まで、他者に伝達するかを自ら決定する」権利。
討議の到達から
1.
-
診療契約とインフォームドコンセント
〔00準備会主催学習会~医療過誤事件からみる「患者中心の医療」とは何か?より〕
医療行為は、身体への侵襲(傷つけること)を伴うが、病気を治すという目的において、患者の合意があって正当性が認められる(診療契約の成立)。患者に十分に説明し納得が得られていなければ傷害罪になる可能性があり、逆にインフォームドコンセントが適切に実施されれば、患者の満足や患者との協同による適切な医療を実施することができる。
2.
-
診療契約のあり方
〔01第1回エホバの証人の輸血拒否患者への対応 P3〕
患者が「病院に来る」という行為によって「診療契約」が発生していると考えることができる。診療契約のうち、完治することを目的とする【請負契約】とで、できるだけ良い状態になることを目指す【委任契約】があり、多くは【委任契約】の形をとることになるが、基本的な治療方針の合意ができなければ契約は成立しない。患者が請負契約を望み、当院がそれに応じられない時は、他院への紹介など責任をもって行う必要がある。
3.
-
患者の自己決定を保障する最適な情報
〔01第1回エホバの証人の輸血拒否患者への対応 P2〕
現在社会で通用している治療上の情報のうち、最適と思われるものをさす。必ずしも最高水準ということではない。具体的には診断と現症状、それに対するどんな治療方法があるか、各方法の危険度、予後と将来予測などを含めて情報提供し選択することができることをいう。当院が提供できないものも含め、そこでできる適切なことはなにかを考える。
4.
-
自己決定に必要な情報
〔09第4回がん化学療法に関る倫理的問題について考える P25〕
提供する情報は、多いほどいいとは限らない。現在の日本における医療水準と照らし合わせて妥当な治療法を、当院にできること以外の情報も含め提供する必要がある。しかし、多くの情報は治療の効果に偏りがちで、不利益となる情報が正しく提供されていない。医療従事者が提供する情報は、患者の判断に大きく影響する。患者が自身の価値観に照らして治療のリスクベネフィット(危険/便益)が考えられる客観的な情報の提供に努める必要がある。
5.
-
インフォームドコンセントの技術
〔05第1回、第2回医療安全室へ寄せられた事例の検討 P7〕
医療の結果についての医療者の予測と患者の期待には差がある。その差を認識した上でインフォームドコンセントなどを行わなくてはならない。インフォームドコンセントは、コミュニケーションにより患者の自己決定権を支援するということであり、多くの情報を持つ医療者が意見を伝えることからコミュニケーションが始まる。倫理的な視点だけでない「技術」が必要である。話し方や表情などが優れた人の技能を模倣することや、模擬学習なども大切である。
6.
-
精神疾患を有する患者の意思確認と自己決定
〔02第1回精神疾患と身体疾患を合併する患者の治療 P2〕
ほぼ9割の患者は通常の意思疎通が可能であり、特別な配慮を必要としない。精神科患者の多くにみられる特徴として変化や不意打ちに弱く、防御反応で攻撃的になることがある。特別視せず他科の患者と同様に対応することが重要である。
7.
-
未成年者の自己決定
〔01第1回エホバの証人の輸血拒否患者への対応 P3〕
患者が未成年であっても自己決定権が優先される。保護者の同意が得られない場合や、近親者が反対する事も予測される場合にも、医療者は本人の意思が貫けるよう最後まで追及する必要があります。
8.
-
患者にとってのプライバシー
〔01第3回医療におけるプライバシーの保護と安全性 P9〕
プライバシーは基本的人権のひとつであり、個人情報を自己コントロールできる権利ととらえることができる。
9.
-
医療の安全性とプライバシー
〔01第3回医療の安全性とプライバシーを考える P15〕
「より制限的でない」「必要最小限で」「他に方法がないか」を丹念に選ぶ必要がある。「安全確保のために違和感を我慢してもらう」一方的な提起とならないよう、利用者の納得を得ることが必要。
10.
-
病院という環境下での一定の権利の制約
〔01第3回医療におけるプライバシーの保護と安全性P9,03第3回医療の安全性とプライバシー P14〕
治療を行なう上で、一定の制約を受けるのはやむをえないことであるが、患者がその権利をどこまで放棄しているのかを確認することが必要である(契約)。医療者側は「患者が自己コントロールする権利を放棄し、医療者側に管理をゆだねた情報」を活用し、適正で最大効果が発揮できるようにする義務がある。
11.
-
緊急やむをえない場合の拘束を容認する3つの要件
〔02第4回身体拘束 P24〕
目的の必要性と手段が正当であることが前提で、切迫性、非代償性、一時性のすべてを満たすことが必要である。
切迫性:本人または他者の生命の危険が迫っているか
非代償性:拘束以外にとりうる方法がないか
一時性:可逆的な方法かつ最小限の期間であるか
12.
-
面会制限は患者の人権に関わる問題
〔09第2回患者の人権や尊厳に配慮した感染対策を探る P11〕
面会制限は、社会からの隔離の形態のひとつといえる。身体拘束における考え方に共通する、切迫性・一時性・非代償性の原則に基づき感染対策の手段の正当性を考えることが大切といえる。さらに、感染対策は患者本人だけの問題ではなく他の患者にも影響が生じるため、「説明と同意」そして「協力」が不可欠である。
13.
-
終末期を考える基本的視点
〔02年度公開倫理委員会 P28,45〕
「人間らしく死ぬ」ことではなく、死に至る過程を「人間的に生きる権利」を貫くこと。医療側からの見方でいうと、終末期の患者を「死にゆく人」と見るか「尊厳ある生き抜く人」と見るかという違いとなる。
14.
-
「ヒトという動物」としての死と「人」の死
〔08第4回終末期における延命治療 P22〕
生き物としての「死」に向かう過程を、いかにその人の尊厳を保ち、望む最期を向かえることができるかという視点を常に持つことが大事である。
15.
-
「延命」と「救命」
〔08第4回終末期における延命治療 P22〕
ある医療行為が無益な延命をもたらすものか否かは、一人ひとりの状態によっても異なる。医学的に見て終末期であるかどうかという点は客観的な基準のひとつであるが、無益であるかどうかは、患者自身が望む生活(生命)の質がどのようなものであるかといった価値観によっても異なる。
16.
-
DNAR
〔05第5,6回DNARガイドライン作成についての答申 P25〕
Do Not Attempt to Resustateの略で、蘇生する可能性が極めて低い状態に対して「心肺蘇生を試みることを差し控える」ことをいう。現時点での日本での標準的な治療を行っても回復せず、死期が迫っている患者が、「心臓マッサージや人工呼吸器等で心肺蘇生法を試みることをして欲しくない」と望まれた場合に、それを医療者に指示しておくことである。
17.
-
退院時に必要なのはDNARの継続ではなく療養の継続性
〔10第2回終末期における退院後の療養の継続性について P11〕
DNAR指示後に回復し退院となるケースでは、退院時の病状評価に基づき、予測される事態(原疾患の悪化または合併症・随伴症状発現や場合によっては事故)への対処方針や具体的な処置等に関して、患者・家族が納得できるよう十分説明し療養担当者間で確認事項の申し送りを確実に行う。
退院後は、退院後の担当医が最新の病状評価を行い、家族や療養・介護に関わる関係者間で情報を共有しておく。また再度入院となり、死が切迫していると判断された場合には、あらためて今回の病状評価および患者(場合によって家族)の意向にもとづき、DNAR指示を行う。
18.
-
終末期要望書の扱い
〔01第5回高齢者の終末期P14,02第5回患者の意思を尊重するとはP17, 04終末期要望書の検討 P35〕
法的な拘束力を持つものではない。様々な終末期という場面を想定することが大事であり、本人の意思はその時の状態や状況により変化するため、各局面での意思確認を行う必要がある。その手段を考えることが先決である。
要望書のみに頼るのではなく、医療サービスの提供として、インフォームドコンセントの視点で考える必要がある。
19.
-
終末期要望書の作成と運用の考え方
〔10第2回終末期における退院後の療養の継続性について P11〕
終末期のケアに関する要望を表明したい(伝えたい)場合の書類として「終末期要望書」を作成する場合は、個別の医療処置の希望の有無ではなく、基本的な価値観や考え方を書ける(または選択肢から選べる)ようにするべきである。病態の進行状況、他の身体機能の残存状況により、QOLの改善や維持が期待できる、とりうる医療処置の選択肢も異なるからである。このような文書を「DNAR」と称するべきではなく、また「事前指示書」と称することも、趣旨が誤って認識される可能性があり極力避けるのが望ましい。
状態が変化するごとに対応の方針を確認するべきであり、利用者・家族と医療者での話し合いを重ねることで情報を共有し、信頼を深める作業が必要である。一度に全ての医療処置についての今後の方針を決めるべきではなく、本人の基本的な価値観・意向に基づいて、治療・ケアの選択肢を個別に検討しながら適応する。
20.
-
患者の「最善」を尊重する
〔09第4回がん化学療法に関る倫理的問題について考える P25〕
QOLを考えるうえでは主観的な側面も重要である。患者自身が選択する権利があり、医療者には一見「合理的でない」と見える選択をするのも患者の権利である。一方で、選択後も患者や家族の気持ちは常に揺れ動いている。患者が決めたことを後悔しないですむサポートが医療者には求められる。
21.
-
個々の患者における栄養療法の意義
〔07第4回終末期の栄養療法について P20〕
一般的には、終末期に過剰な輸液や栄養投与は不要であるといわれている。必要な栄養量を補うことで意識がはっきり等の効果がみられた例や、延命が期待できると思われた事例もあることから、終末期だからと一律に考えるのではなく、個々の患者に対し多職種の知識や専門性を持ちより、柔軟に対応していく必要がある。
22.
-
カンファレンスに臨む視点
〔03第1回各職種の倫理教育・研修とカンファレンス P1〕
「患者の権利章典に基づく医療を実践する」という医療生協の理念にそって患者の問題を検討し専門的技術・能力と感性を患者のために生かす。「これだけは讓れない」を最低線として、「患者のために最善・最高の医療を追求する」姿勢で臨む。
23.
-
専門性(技術)の研鑚
〔03第1回各職種の倫理教育・研修とカンファレンス P2〕
専門職種はその専門性・立場を自覚・明確化し、その技術・能力と感性を磨くことが重要であると同時に、豊かな人間性を身に付けることも必要である。
24.
-
気になる患者をフォローする
〔08第1回気になる患者をフォローするとは P7〕
「気になる」ということは、患者の療養上の問題を発見し解決を援助する医療者の役割を発揮しようとすることから生じる。「気になる」なり方の違いは、情報を収集し問題を発見する力、将来を創造する力、パーソナリティと経験(成功または失敗)とも関わる。そして感受性(気になる力)は、共有しフィードバックされる環境がなければ、低下していく可能性がある。
25.
-
患者の権利
〔03第5回(公開)インフォームドコンセントの完全実施のために~医療訴訟、紛争事例から P29〕
医師(医療者)に対して行使する権利ではなく、協同を求める権利と言える。
26.
-
組合員の利益と病院の機能分化・医療連携の意義は、組合員の「健康主権」、「参加と協同」の取り組みを地域で発展させること
〔09第1回医療生協における機能分化と組合員の利益 P3〕
医療従事者をどれだけ増やせば全組合員の全てのニーズに応えられるのか、ということを考える必要がある。急性期患者の受入れ能力を高めることで、「埼玉協同病院をふだん利用できない組合員も利益を享受することができる」という視点を持つ必要がある。
また、埼玉協同病院が日常の医療活動や患者・組合員との交流・懇談を通して地域の中での存在感を高めることは、人権とくらしを守る運動を広げることにつながる。そのためには、医療連携のネットワーク形成(医療機関の機能に応じた使い分け)に組合員自身が主体的に関わり、患者の権利章典が生きる医療を実現していくことが重要である。組合員の利益とは、「健康主権」、「参加と協同」のとりくみをより発展させることで生み出される価値といえるかもしれない。
27.
-
「被害者が相手の言動を不快に感じた段階でセクシュアルハラスメントである」という共通認識を、病院全体で持つための学習が必要である。
〔10第4回患者から受けるセクシュアルハラスメントに関する対応について P29〕
一般的に信頼関係が構築されていても外見や容姿のことを話題にすることがタブーであること、公的な場所で他人に対しておこなわない言動など、基本的なルールがあることを確認するなど、定期的な教育や研修を通して周知・啓発に努めることが必要だと考える。また、認識を共有する機会を持つことで職員が安心して報告できる環境の整備につながると考える。
28.
-
ドナーとレシピエントの両方を大事にする視点
〔10第2回臓器の移植に関する法律「改正」の問題点と対応について P8〕
臓器を「必要とする」人と「提供したい」人がいてその技術があるのだからよいとする論理は、ドナーを「レシピエントを救うための道具」に格下げし人権を軽視することにつながる。他人の死を前提とし、あるいは健康な人を傷害するという点で、移植医療はやはり特殊な医療といえる。移植以外の治療やケアの可能性も探り、患者にとって最善の結果が得られるような努力やその成果を集積するなどの課題を、世に問うていく必要もある。ドナーとレシピエントを平等に大切にする視点を常に喚起し、知見の蓄積や事実の把握につとめ、医療者としてもっと深めるべき課題である。
- ホーム
- 用語の注解