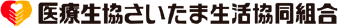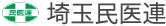- 専門医シリーズ41
- 専門医シリーズ40
- 専門医シリーズ39
- 専門医シリーズ38
- 専門医シリーズ37
- 専門医シリーズ36
- 専門医シリーズ35
- 専門医シリーズ34
- 専門医シリーズ33
- 専門医シリーズ32
- 専門医シリーズ31
- 専門医シリーズ30
- 専門医シリーズ29
- 専門医シリーズ28
- 専門医シリーズ27
- 専門医シリーズ25
- 専門医シリーズ24
- 専門医シリーズ23
- 専門医シリーズ22
- 専門医シリーズ21
- 専門医シリーズ20
- 専門医シリーズ19
- 専門医シリーズ18
- 専門医シリーズ17
- 専門医シリーズ16
- 専門医シリーズ15
- 専門医シリーズ14
- 専門医シリーズ13
- 専門医シリーズ12
- 専門医シリーズ11
- 専門医シリーズ10
- 専門医シリーズ9
- 専門医シリーズ8
- 専門医シリーズ7
- 専門医シリーズ6
- 専門医シリーズ5
- 専門医シリーズ4
- 専門医シリーズ3
- 専門医シリーズ2
- 専門医シリーズ1
命の拍動に寄り添い、 地域の暮らしを 支える

専門医シリーズ40
三友 悟 医師
プロフィール
<認定資格>
日本内科学会総合内科専門医・内科指導医
日本循環器学会循環器専門医
日本心血管インターベンション治療学会認定医
Fellow of European Society of Cardiology
Fellow of American College of Cardiology
<経歴>
2007年 弘前大学医学部卒業
2007年 埼玉協同病院 初期研修医
2009年 新東京病院 心臓内科 医員
2016年 Clinical reseach fellow(IRCCS San Raffaele Scientific Institute Milan,Italy・EMO GVM Centro Cuore Columbus Milan,Italy)
2018年 新東京病院 心臓内科医長・治験管理室長
2024年 川﨑幸病院 循環器内科 副部長
2025年 埼玉協同病院勤務
循環器内科は、心臓疾患や動脈硬化性疾患を扱う領域です。三友医師は、医学生時代に循環器領域を専門とする医師になろうと決めました。その理由は、循環器(心臓や血管)が、人間の身体のなかで最もダイナミックな臓器であると感じたからと言います。「まさに1日10万回も拍動して血液を循環させている―私たちが正しいことをすればその機能は適正に改善や維持される事につながり、間違ったことをすれば命に関わるようなことにつながっていきます。そして心臓が全身に影響を及ぼす臓器であるように、心臓もまた全身から影響を受けています。心臓を取り囲む環境をより良く保つことの大切さもまた、皆さんに感じていただきたいと思っています」
循環器疾患に携わる医療者にできること
循環器領域には、ひとたび発症すれば命に関わり、突然思い描いていた生活や人生が断ち切られてしまう疾患がたくさんあります。「できるかぎりそれを回避するために私たち医療者は、患者さんやご家族がどういう人生を歩みたいと思い描いていらっしゃるのか、何を大切にされているのかを知り、患者さんの希望に対して“医学として”何が提供できるのかを考え診療に当たる必要があると思っています。循環器診療で携わる患者さんの多くは、後期高齢者に近い方々です。その“人生の大先輩”に対して、「あれはダメです」、「これはダメです」などと申し上げる事は、とてもおこがましい事だと思っています。しかし、医師として、特に生命に関わる循環器疾患を扱う者として、ひとたびその患者さんに関わるとしたら、それは患者さんの人生そのものをお預かりし、責任を持つ事だと考えています。ですから、患者さんやご家族から、その責任をお任せいただける信頼関係を築く事ができて初めて、患者さんが「より良い生活」や「思い描いた人生」を過ごせるように、一緒に考える事ができる立場になれるのだと思います。人生の主役はあくまで患者さん自身であり、その価値観や思いを尊重しながら、「あれやこれはできない」ではなく、できれば「どうしたら、あれもこれもできるのか」を一緒に考えたいのです。そして、私たち医師は科学者ですから、常に十分な知識と技術を研鑽し、常にそれら「医学」としての選択肢を十分にご提示できる準備をした上で、最後にそれを選択されるのは患者さんやご家族です」
これから私が力を尽くしたい場所

三友医師は18年前、埼玉協同病院で初期研修を行い、その後より専門的な研修のために急性期の循環器疾患を多数診療する病院へと移りました。以来、狭心症や心筋梗塞など虚血性心疾患に対するカテーテル治療に力を入れながら、循環器領域の急性期治療に関わってきました。そして、無我夢中に目の前の急性期医療に携わって15年が経過し、はたと気付いた事がありました。それは、「『もっと学びたい、もっと技術を磨きたい』というように、いつしか自分ばかりにベクトルを向けてしまった15年であった」という事です。そんな考えを巡らせながら周囲を見渡せば、当時自分が身を置いた急性期医療の現場は、多くの優れた人材やさまざまな力が結集されて成り立っていた現場です。事実、自分が離れた今も、変わらず毎日素晴らしい医療が提供されています。一方、私の地元の秩父をはじめ、自分の足元には、まだまだ「誰かがいないと成り立たない医療」の現場が広がっている事にも、改めて気付く事となりました」
今、埼玉協同病院での診療を主としながら、週に1回地元の同級生のクリニックにおいて診療しています。「埼玉協同病院には、初期研修当時にもお世話になった金子史先生が、厳しい人員態勢のなか築かれてきた循環器診療があります。もし、私にお手伝いさせていただける事があり、それによって一人でも多くの患者さんを診療させていただく事が可能になるのであれば、今まず自分が伺う場所はそこなのではないかと考えました」
そして秩父には、循環器の専門的な診療が難しい状況がありました。「循環器の急性疾患を発症しても、1時間以上かけて遠方の救急病院まで行かなければならない。それでは助からない生命もあります。もし、それがもっと早い段階で診療へ繋ぐ事ができれば、さらに、もし将来的にそれらを予防する方向で診療できれば、と思うのです。また、日常的に心不全症状があっても、「歳のせいかな」と、家族やかかりつけ医の先生にも相談できず、徐々に進行してしまった結果、有効な治療を受ける期を逸してしまっている症例も少なくありません。しかし例えば、畑仕事は辛くなってきたけど、作った野菜を離れて暮らす娘さんに送るのが一番の喜びであるという方、動くと息切れはするけどご主人との旅行だけが楽しみであるという方、せめて最期に孫の結婚式には出席したいとおっしゃる方。そうした思いが少しでも叶えられるように、一人ひとりの患者さんが思い描いた豊かな人生を送れるように、私にできる循環器診療を通じて携わりたいと思っています」
時を経て埼玉協同病院で再び診療に当たる今、「初期研修を終えてここを離れるとき、力をつけ診療を手伝える存在となっていつか戻ってこようと考えていたこと」を、三友医師は改めて思い出しています。
【地域の開業医の方々へのメッセージ】
環器内科医師が2人となり、これまで以上に診療態勢を確保できるようになりました。患者さんの循環器系のトラブルについてぜひ、私たちにご相談ください。
関連ページ