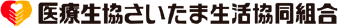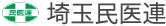- 専門医シリーズ41
- 専門医シリーズ40
- 専門医シリーズ39
- 専門医シリーズ38
- 専門医シリーズ37
- 専門医シリーズ36
- 専門医シリーズ35
- 専門医シリーズ34
- 専門医シリーズ33
- 専門医シリーズ32
- 専門医シリーズ31
- 専門医シリーズ30
- 専門医シリーズ29
- 専門医シリーズ28
- 専門医シリーズ27
- 専門医シリーズ25
- 専門医シリーズ24
- 専門医シリーズ23
- 専門医シリーズ22
- 専門医シリーズ21
- 専門医シリーズ20
- 専門医シリーズ19
- 専門医シリーズ18
- 専門医シリーズ17
- 専門医シリーズ16
- 専門医シリーズ15
- 専門医シリーズ14
- 専門医シリーズ13
- 専門医シリーズ12
- 専門医シリーズ11
- 専門医シリーズ10
- 専門医シリーズ9
- 専門医シリーズ8
- 専門医シリーズ7
- 専門医シリーズ6
- 専門医シリーズ5
- 専門医シリーズ4
- 専門医シリーズ3
- 専門医シリーズ2
- 専門医シリーズ1
子どもの健康を見守る地域の拠点

専門医シリーズ37
荒熊 智宏 医師
プロフィール
<認定資格>
日本小児科学会専門医、日本小児神経学会専門医
<経歴>
2001年 群馬大学医学部 卒業
2001年 埼玉協同病院 勤務
2005年 埼玉医科大学総合医療センター小児科 研修
2006年 埼玉協同病院 勤務
2011年 東京都立小児医療センター神経内科 研修
2013年 埼玉協同病院 勤務
地域に医療が維持される必要性
荒熊医師は、怪我や風邪などで医療機関にたびたびお世話になる、ちょっと注意力散漫でおちつきのない少年でした。また斜視があり、幼稚園のときには入院して眼科手術も経験しました。
生まれ育った町には当時、町立診療所があり年配の女医さんが1人で診療に当たっていました。そこで医療事務の仕事をしていたのが荒熊医師の母親でした。「時に自治医科大学から応援の医師が来て、なんとか回している診療所。過疎ではないけれど、小さな地域で必要な医療を維持する大変さを、自分も患者になる機会が多かった分だけ感じ取っていました。だから将来、医療に関わる仕事がしたいと小学生の頃には思っていました」
子どもたちに関わる仕事をしたい !
医学生になってからは、糖尿病の子どもたちとのキャンプに参加したり、小児病院で「おもちゃ図書館」を開いて子どもたちと遊んだりなどのボランティア活動に積極的に関わっていきました。その中で、「子どもたちに関わる仕事」に強く惹かれていきます。「学校の教師や保育士という選択肢もあると本気で迷った時期もありました。しかし悩んだ末、医学の勉強を始められたのだから、小児科医として子どもたちと関わろうと心を決めました」
高校3年生のときに「医師体験」で訪れた縁から、医学部を卒業後、埼玉医協同病院で働き始めます。内科や外科などの研修を積んだうえで、4年目から小児科医の道を歩き出しました。
成長の瞬間に出合う―小児科医の喜び

小児科医の魅力は「子どもたちの健康を守りながら成長する姿を見られること」と荒熊医師は言います。小児科では子どもが小さいうちは、治療に関して保護者とのやりとりが主になります。それが小学校高学年、中学生になってくると治療の主体を子ども本人に変えていきます。「そのタイミングが難しいのですが。こういう病気だから、こういう薬や治療が必要なんだと、本人と向き合い、話し合えるようになっていきます。そのプロセスで、子どもの身体と心の成長・発達を感じます。小さな頃から見守ってきた子どもが、成長して羽ばたいていく瞬間に出合う。それが小児科医の何よりの喜びです」
子どもの成長をゆっくりと待てる社会に
不登校や発達障害のある子どもが増えていると言われています。荒熊医師は子どもの特性や疾患の変化の他、それをどう受け入れるか社会の側の要因も大きいと指摘します。「今、多様性を謳う社会ですが一方で、親も学校も子どもたちに対してじっくり待てずに、すぐに白黒をつけたがる傾向があります。できないこと、発達の遅れに、社会の側が過敏に反応しすぎていると感じます」
たとえば自閉症の子どもたちは、「自閉症スペクトラム」と言われるように、その症状には大きな幅があります。「だから検査で○点以上は障害です、診断がつきますという単純な話ではありません。重要なのは診断そのものではなく、その子どもが社会生活を送るうえで障害のせいで伸び悩んでしまうかどうかを見極めて、必要なアプローチをしていくことです」
荒熊医師は、ここで診療を継続することを自分の役割として大切に考えています。「子どもに関わるということは、短期間で終わらせられるものではありません。一進一退しながら成長していく姿を、同じ場所にいて途切れずに見守り続ける、それを大事にこれからもやっていきます」
お休みの日は何を?「浦和のサッカーチームのファンで、近所の友達とよく試合を観に行きます。あとは基本、家でゴロゴロするのが好きですね」楽しそうにサッカーの話をされます。子どもたちにきっと大人気の、優しい笑顔でした。
【患者さんへの一言メッセージ】
小児科は病気も診るし困りごとの相談にものる、そういう多面的な機能を持った存在として活用してほしい。子育てはたいへんだけど、子どもたちは時間と共にその子のペースで確実に成長していきます。だからぜひ、肩の力を抜いて、ゆったりした気分で子育てを楽しんでみてください。
関連ページ